
撮影は1年前の2015年3月から始めました。ちょうど昨年の今頃は、栃木県足利市で、映画の冒頭に出てくる日の丸の旗が掲げられた道路のシーン(昭和64年の時代風景)を撮影していました。その前日は、群馬県の吾妻川の奥、それこそ八ツ場ダム予定地の近くで、スーツケースを落とすシーンを撮っていました。古い街並みを探して、ロケ先も多岐にわたりましたね。この1年は、ほぼ『64-ロクヨン-』の仕事しかやっていなかったので、あっという間でした。
僕はミステリーが好きなので、発刊されてすぐに読みました。警察の広報官という主人公の設定が面白いし、昭和64年というテーマを表している「ロクヨン」というタイトルがかっこいいと思いましたね。
あと、その土地の風土や時代背景と、作品の内容がマッチしているという点も興味深いです。原作で登場する漬物屋は、群馬県の藪塚あたりがモデルだと思うのですが、昔から漬物屋が多い地域です。映画では設定通りの場所で撮影できなかったので、同様に漬物屋が多い地域である埼玉県深谷市で撮影しました。漬物屋が多い理由としては、もともと農家が多くあり、戦後の食糧難の時に、野菜の余りもので半加工品を作る仕事をする人が増えたことが関係しているようです。つまり原作者の横山さんは、漬物屋の設定ひとつとっても、戦後の群馬の貧しい環境と土地の関係を調べて書いているということが分かります。
また、原作には“風が舞って砂埃が口に入ってくる”という表現がありますが、確かに群馬県は地理的特徴として風がとても強いです。地域風土と作品の内容がマッチしているという点で、横山さんの原作は素晴らしいです。そういう背景、風景をきちんと映像化したいという思いがありました。
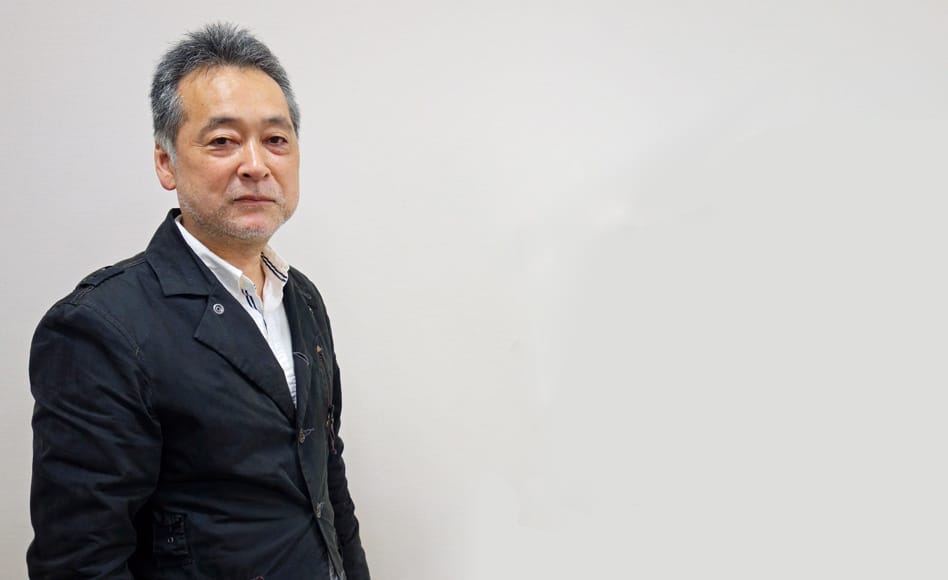
原作は一人称で書かれていて、最後の方は、三上(佐藤浩市)が頭の中で妄想を繰り広げて犯人にたどり着くんです。ただ映画では心の中を、アクションや、人と人とのぶつかり合いで表現しなければならない。そこは代えさせてくださいとお願いしました。いろんなパターンを横山さんにお見せして最終的にこの形になりました。
脚本の久松真一さんが、僕がこの作品に入る前からやられていたので、構想期間は長かったと思います。あの長大な前後編をまとめるのは大変な労力だったと思うので、久松さんがあってこその映画化です。本作を手掛ける前もずっとテレビで横山原作の仕事をされていたから、横山さんのことをよく分かっていらしたのも、よかったと思います。
役者さんが対峙しあって自分の気持ちをぶつけ合うというシーンが多いので、芝居対決、演技と演技とのぶつかり合いというところですね。役者同士が、どれだけ役と役の中でぶつかり合い、感情を高め合っていくかというのは、この作品の一番の見どころだと思います。

前編のラストの方で、三上(佐藤浩市)が記者クラブに向かって一人で話すシーンです。記者それぞれが感情移入していくところだと思うし、それに至る過程がいいですよね。
本作をご覧になる方はよく豪華キャストに注目されますが、実はインディーズで頑張っている若い役者さんたちが一生懸命、佐藤浩市さんに対して喧嘩を張り、向かい合った芝居をしているところが、醍醐味だと思います。言い方に語弊があるかもしれませんが、メジャーとマイナーの垣根を超えて一つのシーンになっているところが、この映画が持っている力の一つではないかと思います。
新聞記者の方を呼んで、ノウハウや心構え、基本的なメモの取り方、情報開示はどこまでOKか等、リアルな話をして頂きました。劇中では激しい言い合いがありますが、実際にもありえるのかというような事もふくめ、勉強会みたいなものですね。映画ではアドリブも多かったです。

やはり群馬県警のシーンを撮影した、旧長岡市役所ですね。取り壊しが決まっていたため、撮影のために部屋の中を変えていいという許可を頂けたのですが、あそこが見つかっていなかったら本作は予算オーバーして、大変なことになっていたでしょうね。東京から遠くに行くほど予算がかかるので、新潟県が遠出ロケできるギリギリの距離でした。
広報室と記者クラブ室は、壁が取り外せる広い場所にセットを作っています。前編の最後で三上(佐藤浩市)が記者クラブの皆に向かって話しているシーンは、望遠で撮影しています。そうすると画がきゅっとつまって、広角じゃないからカチッとした画が撮れるんです。壁を外してできた奥行は、映画をよく知っている人じゃないと分からないのですが、浩市さんはそういうカットが好きなので「これは映画屋がみたら、びっくりするなあ」と凄く喜んでいました(笑)。
――後編の見どころはやはり、三人の男(佐藤浩市さん、緒形直人さん、永瀬正敏さん)それぞれのぶつかり合いですか?
そこだと思います。緒形さんも永瀬さんも鬼気迫る芝居をしていましたから。緒形さんは、気持ちを高めるために、自腹で現場に前乗りして前泊していましたよ。

この『64―ロクヨン―』という映画は、みなさんがもっている“忘れてはいけないもの・忘れられないもの・その人にとって大事なもの”を大切にしている作品だと思います。時代に取り残されたかのように、それぞれが胸の中でずっと抱えている思いを、共有しようとしています。
東日本大震災を経験し、今回の熊本地震、今なお大変な思いをされている方が多くいらっしゃると思いますが、僕たち日本人が、これからどうやって生きていこうかと考える時、この作品を通じて何かを感じていただけたらうれしいです。
正直な人ですね。自分の意見を持っているのはもちろんですが、現場では、嘘をつかれると困るんですよ。失敗は改善できるから良いけれど、嘘をつかれると改善できない。すべてのことがそうだと思いますが、正直に自分の意見を伝えてくれたりすると、僕たちも受けとります。
作り手としては当然だと思いますが、自分が正直でないとモノは作れないし、正直であることはやはり大切だと思います。
――ありがとうございました。

撮影は1年前の2015年3月から始めました。ちょうど昨年の今頃は、栃木県足利市で、映画の冒頭に出てくる日の丸の旗が掲げられた道路のシーン(昭和64年の時代風景)を撮影していました。その前日は、群馬県の吾妻川の奥、それこそ八ツ場ダム予定地の近くで、スーツケースを落とすシーンを撮っていました。古い街並みを探して、ロケ先も多岐にわたりましたね。この1年は、ほぼ『64-ロクヨン-』の仕事しかやっていなかったので、あっという間でした。
僕はミステリーが好きなので、発刊されてすぐに読みました。警察の広報官という主人公の設定が面白いし、昭和64年というテーマを表している「ロクヨン」というタイトルがかっこいいと思いましたね。
あと、その土地の風土や時代背景と、作品の内容がマッチしているという点も興味深いです。原作で登場する漬物屋は、群馬県の藪塚あたりがモデルだと思うのですが、昔から漬物屋が多い地域です。映画では設定通りの場所で撮影できなかったので、同様に漬物屋が多い地域である埼玉県深谷市で撮影しました。漬物屋が多い理由としては、もともと農家が多くあり、戦後の食糧難の時に、野菜の余りもので半加工品を作る仕事をする人が増えたことが関係しているようです。つまり原作者の横山さんは、漬物屋の設定ひとつとっても、戦後の群馬の貧しい環境と土地の関係を調べて書いているということが分かります。
また、原作には“風が舞って砂埃が口に入ってくる”という表現がありますが、確かに群馬県は地理的特徴として風がとても強いです。地域風土と作品の内容がマッチしているという点で、横山さんの原作は素晴らしいです。そういう背景、風景をきちんと映像化したいという思いがありました。
原作は一人称で書かれていて、最後の方は、三上(佐藤浩市)が頭の中で妄想を繰り広げて犯人にたどり着くんです。ただ映画では心の中を、アクションや、人と人とのぶつかり合いで表現しなければならない。そこは代えさせてくださいとお願いしました。いろんなパターンを横山さんにお見せして最終的にこの形になりました。
脚本の久松真一さんが、僕がこの作品に入る前からやられていたので、構想期間は長かったと思います。あの長大な前後編をまとめるのは大変な労力だったと思うので、久松さんがあってこその映画化です。本作を手掛ける前もずっとテレビで横山原作の仕事をされていたから、横山さんのことをよく分かっていらしたのも、よかったと思います。
役者さんが対峙しあって自分の気持ちをぶつけ合うというシーンが多いので、芝居対決、演技と演技とのぶつかり合いというところですね。役者同士が、どれだけ役と役の中でぶつかり合い、感情を高め合っていくかというのは、この作品の一番の見どころだと思います。
前編のラストの方で、三上(佐藤浩市)が記者クラブに向かって一人で話すシーンです。記者それぞれが感情移入していくところだと思うし、それに至る過程がいいですよね。
本作をご覧になる方はよく豪華キャストに注目されますが、実はインディーズで頑張っている若い役者さんたちが一生懸命、佐藤浩市さんに対して喧嘩を張り、向かい合った芝居をしているところが、醍醐味だと思います。言い方に語弊があるかもしれませんが、メジャーとマイナーの垣根を超えて一つのシーンになっているところが、この映画が持っている力の一つではないかと思います。
新聞記者の方を呼んで、ノウハウや心構え、基本的なメモの取り方、情報開示はどこまでOKか等、リアルな話をして頂きました。劇中では激しい言い合いがありますが、実際にもありえるのかというような事もふくめ、勉強会みたいなものですね。映画ではアドリブも多かったです。
やはり群馬県警のシーンを撮影した、旧長岡市役所ですね。取り壊しが決まっていたため、撮影のために部屋の中を変えていいという許可を頂けたのですが、あそこが見つかっていなかったら本作は予算オーバーして、大変なことになっていたでしょうね。東京から遠くに行くほど予算がかかるので、新潟県が遠出ロケできるギリギリの距離でした。
広報室と記者クラブ室は、壁が取り外せる広い場所にセットを作っています。前編の最後で三上(佐藤浩市)が記者クラブの皆に向かって話しているシーンは、望遠で撮影しています。そうすると画がきゅっとつまって、広角じゃないからカチッとした画が撮れるんです。壁を外してできた奥行は、映画をよく知っている人じゃないと分からないのですが、浩市さんはそういうカットが好きなので「これは映画屋がみたら、びっくりするなあ」と凄く喜んでいました(笑)。
――後編の見どころはやはり、三人の男(佐藤浩市さん、緒形直人さん、永瀬正敏さん)それぞれのぶつかり合いですか?
そこだと思います。緒形さんも永瀬さんも鬼気迫る芝居をしていましたから。緒形さんは、気持ちを高めるために、自腹で現場に前乗りして前泊していましたよ。
この『64―ロクヨン―』という映画は、みなさんがもっている“忘れてはいけないもの・忘れられないもの・その人にとって大事なもの”を大切にしている作品だと思います。時代に取り残されたかのように、それぞれが胸の中でずっと抱えている思いを、共有しようとしています。
東日本大震災を経験し、今回の熊本地震、今なお大変な思いをされている方が多くいらっしゃると思いますが、僕たち日本人が、これからどうやって生きていこうかと考える時、この作品を通じて何かを感じていただけたらうれしいです。
正直な人ですね。自分の意見を持っているのはもちろんですが、現場では、嘘をつかれると困るんですよ。失敗は改善できるから良いけれど、嘘をつかれると改善できない。すべてのことがそうだと思いますが、正直に自分の意見を伝えてくれたりすると、僕たちも受けとります。
作り手としては当然だと思いますが、自分が正直でないとモノは作れないし、正直であることはやはり大切だと思います。
――ありがとうございました。
(STORY)
わずか1週間の昭和64年に発生した少女誘拐殺人事件・通称「64(ロクヨン)」。事件は未解決のまま14年の時が流れ、時効が目前に迫っていた。かつて刑事部の刑事としてロクヨンの捜査にもあたった敏腕刑事の三上(佐藤浩市)は、現在は警務部の広報官として働き、記者クラブとの確執や、県警内の刑事部と警務部の対立などに神経をすり減らす日々を送っていた。そんな中、警察庁長官がロクヨン担当捜査員を視察に訪れることに。複雑に絡み合う問題の収拾に奔走しながら迎えた長官視察の前日。ロクヨンを模したかのような新たな誘拐事件が発生する。
監督:瀬々敬久 原作:横山秀夫『64(ロクヨン)』(文春文庫刊)
出演:佐藤浩市、綾野剛、榮倉奈々、瑛太、永瀬正敏、三浦友和 ほか
前編:公開中
後編:6月11日(土)連続ロードショー
©2016映画『64』製作委員会
瀬々敬久(ぜぜ・たかひさ)監督
1960年生まれ、大分県出身。京都大学在学中から自主映画を製作。『MOON CHILD』(03年)をはじめとする劇場映画からドキュメンタリー、テレビなど様々な作品を発表。『ヘヴンズ ストーリー』(10年)が第61回ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞とNETPAC賞の2冠。『アントキノイノチ』(11年)が第35回モントリオール世界映画祭でイノベーションアワードを受賞している。
